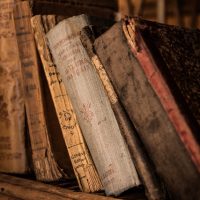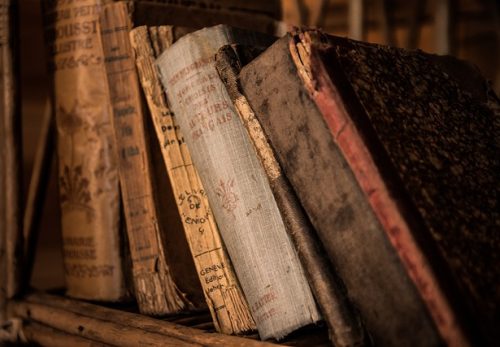インフィード広告とは、Webサイトやアプリのコンテンツとコンテンツの間に表示される広告のことです。
主に、ニュースアプリのフィード(記事一覧)、SNSのタイムライン、コンテンツ主体のウェブサイトの記事一覧などの間に自然に溶け込むように表示されます。
インフィード広告の主な特徴
コンテンツとの親和性: 通常のコンテンツと同じデザインやフォーマットで表示されるため、ユーザーに広告であるという違和感を与えにくく、自然な形で情報を提供できます。
視認性が高い: ユーザーがコンテンツを閲覧する流れの中で自然に目に入るため、他の広告形式に比べて見てもらいやすい傾向があります。
クリックやエンゲージメントの促進: コンテンツに興味を持っているユーザーに対して、関連性の高い広告を自然な形で提示できるため、クリック率やエンゲージメント(いいね、シェア、コメントなど)が高まる可能性があります。
「広告」または「PR」などの表記: 広告であることを明示するために、「広告」「PR」「プロモーション」「Sponsored」といった表記が義務付けられています。
インフィード広告が表示される主な場所
SNS: Facebook、X (旧Twitter)、Instagram、LINEなどのタイムラインやフィード上
ニュースアプリ/キュレーションメディア: Gunosy、SmartNews、Antennaなどの記事一覧やフィード上
ポータルサイト: Yahoo! JAPANなどのトップページや記事一覧
一部のウェブサイト: コンテンツが一覧で表示される形式のサイト
こんなイメージで。

(参考:http://www.yahoo.co.jp/)
インフィード広告は記事と記事の間にしれっと表示されるので
興味ありそうなタイトルだと間違えて押しちゃうこともありますよね。
インフィード広告は、読みたいコンテンツを選んでいる時に広告と分からないように工夫されているため、ユーザーの警戒心が薄れ、クリックを促せるという大きなメリットがあります。
インフィード広告のメリット
ユーザーの広告への抵抗感が少ない: 通常のコンテンツに溶け込んでいるため、広告特有の煩わしさや押し付けがましさを感じさせにくいです。
高いクリック率・エンゲージメント率: コンテンツに興味のあるユーザーの目に触れやすいため、クリックやエンゲージメントにつながりやすい傾向があります。
ブランド認知度の向上: 自然な形でユーザーの目に触れることで、サービスや製品の認知度を高める効果が期待できます。
詳細なターゲティングが可能: 多くのプラットフォームでは、ユーザーの属性、興味関心、行動履歴などに基づいた詳細なターゲティング設定が可能です。
インフィード広告のデメリット
コンテンツと誤認される可能性: 広告であることが分かりにくい場合、ユーザーがコンテンツと誤認してクリックしてしまう可能性があります。これはステルスマーケティングとみなされるリスクもあるため、適切な「広告」表記が重要です。
制作に手間がかかる: 通常のコンテンツとデザインを合わせる必要があるため、バナー広告などと比較して制作に手間やコストがかかることがあります。
効果測定の難しさ: 広告の成果が、広告自体の魅力によるものなのか、掲載面のコンテンツの魅力によるものなのか、切り分けが難しい場合があります。
広告疲れ・不信感: あまりにも広告が多い、あるいはコンテンツと関連性が低い広告が表示されると、ユーザーに不快感を与え、プラットフォーム全体の信頼性を損なう可能性もあります。
インフィード広告とネイティブ広告の関係
インフィード広告は、ネイティブ広告の一種とされています。ネイティブ広告とは、「広告掲載面に広告を自然に溶け込ませることで、ユーザーにコンテンツの一部として見てもらうことを目的とした広告」の総称です。インフィード広告はその代表的な形式の一つと言えます。
インフィード広告は、ユーザー体験を損なわずに効果的に情報を届けることができる広告手法として、多くのプラットフォームで活用されています。ただし、ユーザーに誤解を与えないよう、適切な表示と質の高いクリエイティブが求められます。
サムネイルとタイトルが命
インフィード広告はズバリ「サムネイルとタイトル」が命。
WEBディレクターやマーケッターはこの2つを決めるのに、頭から煙が出るくらい知恵を絞っていることと思います。
誘導してからも勝負なんだけどね
広告はまず押されることが重要だ!
広告は誘導先の内容が重要だ!
この議論を何回したことか。
正直、「両方大事」だと思います。
まさにWEBディレクターの腕が試される施策と言えますね。