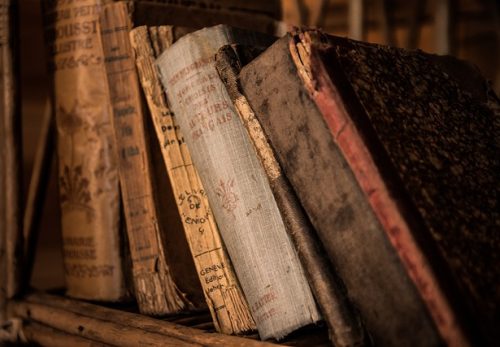リタゲ(リターゲティング)広告とは?
リタゲ広告とは、リターゲティング広告の略称のことで、特定のWEBサイトに訪問したユーザーを追跡して、訪問したユーザーと親和性の高い広告を表示させる仕組みのことです。
Cookie(クッキー)と呼ばれるパソコンに保存された情報を元に、他のサイトに訪問した際にも親和性の高い広告を表示させることができるのです。
この仕組みを使って、ユーザーが欲しい時に、欲しいタイミングで広告が表示されていることで商品・サービスの購入させることができます。
ちなみに、
Yahooリスティングの場合、リターゲティング広告
Google Adwordsの場合、リマーケティング広告
と言いますので覚えておいてくださいね。
なぜ、リターゲティング(リタゲ)広告が注目されるのか
なぜ、リターゲティング(リタゲ)広告が注目されるのかというと、リタゲの仕組みができるまではユーザー属性に合わせた広告を表示させることができないため、経験や勘を頼りに沢山の媒体に広告を数打ちする必要がありました。
リタゲができるようになったことで、ユーザー属性に合わせた商品・サービスをピンポイントで提案できるようになりました。
そして、ユーザーにとっても知りたい情報が提供され、また、企業側にとっても商品・サービスを求めているユーザーに提案できることとなりより便利な社会となったといえるでしょう。
リタゲを始める際に注意するポイントとは?
特に、YahooとGoogleで広告の配信先が異なる点に注目してYahooリスティングを活用するか、Google Adwordsを活用するか選択すると良いかと思います。
リターゲティング広告の仕組み
リターゲティング広告は、主にウェブサイトに埋め込まれた「タグ」と、ユーザーのブラウザに保存される「Cookie(クッキー)」という仕組みを利用して機能します。
タグの設置とCookieの付与:
広告主は、自社のウェブサイトの各ページに、広告配信事業者(Google、Yahoo!など)から提供される専用の「リターゲティングタグ(またはリマーケティングタグ)」を設置します。ユーザーがこのタグの設置されたページを訪問すると、そのユーザーのブラウザに広告配信事業者によってCookieが付与されます。このCookieには、ユーザーがサイトを訪問したという情報などが記録されます(個人を特定する情報ではありません)。
ユーザーリストの作成:
広告配信事業者は、このCookieの情報に基づいて、サイト訪問者をリスト化します。例えば、「商品Aのページを見たユーザー」「カートに商品を入れたが購入しなかったユーザー」といった特定の行動履歴を持つユーザーのリストを作成できます。
広告の再配信:
リスト化されたユーザーが、提携している他のウェブサイトやアプリ(広告掲載枠があるサイト)を閲覧した際に、広告配信事業者はそのユーザーのCookieを認識し、広告主が設定した広告を再度表示します。
リターゲティング広告の種類
リターゲティング広告には、対象とするユーザーの行動やプラットフォームに応じていくつかの種類があります。
標準のリターゲティング(ディスプレイ向けリターゲティング):
ウェブサイトを訪問したユーザーに対して、ディスプレイ広告ネットワーク(様々なウェブサイトやアプリ上の広告枠)で広告を表示します。
検索広告向けリターゲティングリスト(RLSA: Remarketing Lists for Search Ads): 過去にサイトを訪問したユーザーが、後日、検索エンジン(Googleなど)で関連キーワードを検索した際に、検索結果ページに表示される広告の入札単価を調整したり、特定の広告を表示したりします。
動的リターゲティング:
ユーザーが閲覧した特定の商品やサービスに基づいて、関連性の高い広告クリエイティブを自動生成して表示します。例えば、閲覧した商品の画像や価格を含んだ広告を表示できます。
動画リターゲティング:
YouTubeなどの動画プラットフォームで、自社の動画を視聴したユーザーやチャンネル登録者に対して広告を表示します。
アプリのリターゲティング:
自社のスマートフォンアプリを利用したユーザーに対して、再度アプリの利用を促したり、関連情報を提供したりする広告を表示します。
顧客リストに基づくリターゲティング:
企業が保有する既存顧客のメールアドレスなどの情報(個人情報保護法に準拠した取り扱いが前提)を広告プラットフォームにアップロードし、その顧客がプラットフォーム上で特定された場合に広告を表示します。
リターゲティング広告のメリット
高いコンバージョン率:
一度サイトを訪れたユーザーは、自社の商品やサービスに既に一定の興味関心を持っている可能性が高いため、全くの新規ユーザーに広告を配信するよりも、購入や問い合わせといったコンバージョン(成果)に繋がりやすい傾向があります。
見込み客への再アプローチ:
検討段階でサイトを離脱してしまったユーザーや、購入を迷っているユーザーに対して再度アプローチすることで、購買意欲を喚起し、機会損失を防ぐ効果が期待できます。
費用対効果が高い:
関心の高いユーザーに絞って広告を配信できるため、無駄な広告費用を抑えやすく、費用対効果を高めることができます。
ブランド認知度の向上(単純接触効果):
繰り返し広告を目にすることで、ユーザーの記憶に残りやすくなり、ブランドや商品に対する親近感や認知度を高める効果(単純接触効果)も期待できます。
ターゲットの絞り込みの柔軟性:
「特定の商品ページを見た人」「カートに商品を入れたが購入しなかった人」「一定期間内に再訪問がない人」など、ユーザーの行動履歴に基づいて細かくターゲットリストを作成し、それぞれに最適化されたメッセージを配信できます。
リターゲティング広告のデメリット・注意点
ユーザーにマイナスイメージを持たれる可能性:
同じ広告が何度も表示されると、ユーザーに「しつこい」「追いかけられている」といった不快感を与え、ブランドイメージを損なう可能性があります。適切な表示回数制限(フリークエンシーキャップ)の設定が重要です。
新規顧客の獲得には不向き:
あくまでサイト訪問履歴のあるユーザーが対象となるため、全く新しい顧客層を開拓するには適していません。他の広告手法との組み合わせが必要です。
広告配信の初期段階には向かない:
効果的なリターゲティング広告を配信するには、ある程度のサイト訪問者数(リストの蓄積)が必要です。サイト立ち上げ直後など、データが十分にない段階では効果を発揮しにくい場合があります。
プライバシーへの配慮:
ユーザーの行動履歴を追跡することになるため、プライバシー保護の観点から慎重な運用が求められます。プライバシーポリシーでの明記や、ユーザーが広告の追跡を拒否できるオプトアウトの選択肢を提供することが重要です。
運用ノウハウが必要:
効果的なリスト作成、入札調整、クリエイティブの最適化など、成果を出すためにはある程度の運用知識や経験が求められます。
Cookie規制の影響:
近年、プライバシー保護強化の流れから、AppleのITP(Intelligent Tracking Prevention)機能やGoogle ChromeのサードパーティCookie廃止計画など、Cookieの利用に制限がかかる動きが強まっています。これにより、従来のリターゲティング広告の効果が低下したり、計測が困難になったりする可能性があります。
Cookie規制とリターゲティング広告の今後
サードパーティCookieへの依存度が高かった従来のリターゲティング広告は、Cookie規制の進行により、その効果やリーチが制限されることが予想されています。
この「ポストCookie時代」において、広告業界では以下のような代替策や新しいアプローチが模索・導入されています。
ファーストパーティデータの活用:
自社で収集した顧客データ(サイト内行動履歴、購買履歴、CRMデータなど、ユーザーの同意を得て取得したもの)をより積極的に活用する動きが強まっています。
コンテクスチュアルターゲティング:
ウェブページのコンテンツ内容(文脈)をAIなどが解析し、その内容と関連性の高い広告を配信する手法です。ユーザーの閲覧履歴に依存しないため、プライバシーに配慮したターゲティングが可能です。
共通IDソリューション:
複数のパブリッシャーや広告プラットフォーム間で利用可能な、Cookieに代わる新しいユーザー識別技術の開発・導入が進められています。ただし、これもプライバシー保護との両立が課題となります。
広告プラットフォーム独自のソリューション:
Googleの「Topics API」や「FLEDGE (現Protected Audience API)」など、プライバシーサンドボックス構想の中で、個々のユーザーを特定せずに興味関心に基づいた広告配信を目指す技術開発が進んでいます。
まとめ
・ リタゲとは、リターゲティング広告のこと
・ Yahooリスティングの場合、リターゲティング広告、Google Adwordsの場合、リマーケティング広告と呼ばれている。
・ YahooリスティングとGoogle Adwordsで広告の配信先が異なるので商品・サービスによって使い分けるべし
リターゲティング広告は、依然として有効なマーケティング手法の一つですが、Cookie規制などの環境変化に対応し、ユーザーのプライバシーに配慮しながら、より進化した形での活用が求められています。今後は、これらの新しい技術や考え方を取り入れつつ、他のマーケティング施策と組み合わせながら、総合的な戦略の中でその役割を再定義していく必要があるでしょう。