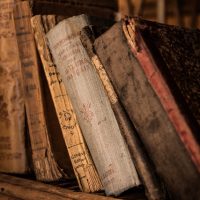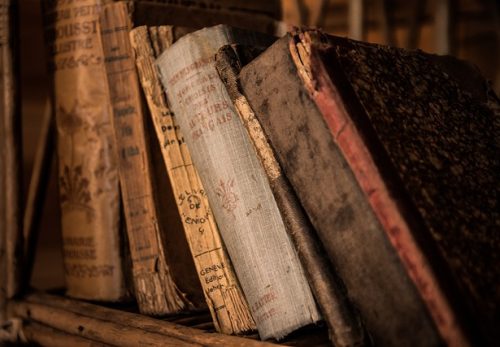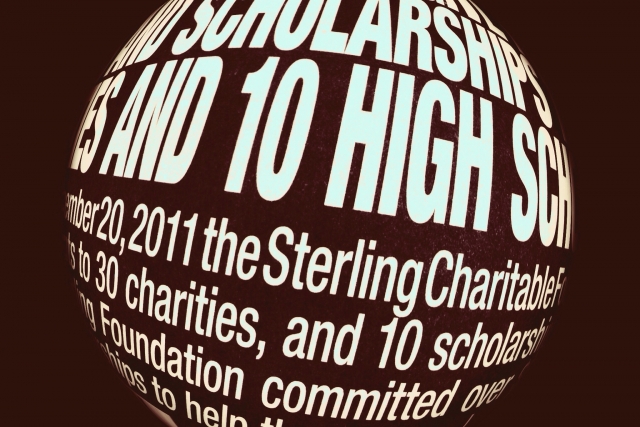みなさまこんにちは。
高橋です。
今回は、リーンスタートアップについて学んでいきたいと思います。
リーンスタートアップとは?
リーンスタートアップとは、事業やサービスを立ち上げる時に最小構成で素早くローンチさせるための手法のことです。
リーンスタートアップはエリック・リース(Eric Ries)により2011年にはじめて提唱されました。
なおリーンスタートアップの「リーン」(lean)には「余分な肉がなく細い」といった意味があります。
リーンスタートアップの基本的な考え方
リーンスタートアップの核となるのは、「構築 (Build) – 計測 (Measure) – 学習 (Learn)」というフィードバックループを高速で回すことです。
1.仮説構築 (Hypothesize) / アイデア (Idea):
まず、製品やサービスが顧客の特定の課題を解決できるか、どのような価値を提供できるかといった仮説を立てます。
2.構築 (Build) / MVP (Minimum Viable Product) の開発:
次に、その仮説を検証するために必要最小限の機能だけを備えた試作品(MVP:Minimum Viable Product)を短期間かつ低コストで開発します。
最初から完璧な製品を目指すのではなく、あくまで検証を目的とします。
3.計測 (Measure) / 実験 (Test):
開発したMVPを実際の顧客に使ってもらい、その反応や行動データを収集・分析します。アンケートやインタビューなども有効な手段です。
4.学習 (Learn) / データ (Data):
計測結果から得られた学びをもとに、当初の仮説が正しかったのか、修正が必要なのかを判断します。
5.意思決定 (Decision):
学習結果に基づき、製品やサービスを改善して再度ループを回す(反復:Iterate)か、あるいは仮説が大きく間違っていた場合は事業の方向性を転換する(ピボット:Pivot)か、場合によっては撤退も視野に入れた意思決定を行います。
このサイクルを繰り返すことで、顧客のニーズを的確に捉え、市場に受け入れられる製品・サービスへと段階的に進化させていくのが特徴です。
リーンスタートアップのメリット
コストと時間の節約: MVPから始めるため、初期投資を抑えられ、開発期間も短縮できます。市場に受け入れられない製品に大きなリソースを投下するリスクを低減できます。
顧客ニーズに沿った開発: 実際に顧客のフィードバックを得ながら開発を進めるため、より顧客の求める製品・サービスを提供しやすくなります。
市場への迅速な投入: 短期間でMVPを市場に出し、検証と改善を繰り返すことで、スピーディーに市場の反応を見ながら事業を進められます。
リスクの低減: 小さく始めて検証を重ねるため、もし失敗した場合でも損失を最小限に抑えることができます。
リーンスタートアップのデメリット・注意点
適さない業界や製品もある: 開発コストが非常に高い製品や、安全性が厳しく問われる分野など、MVPでの検証が難しい場合があります。
当初の目的を見失う可能性: 顧客のフィードバックに過度に対応しすぎると、本来目指していたビジョンから逸れてしまうことがあります。
SNSなどによる急速な顧客離れのリスク: 未完成なMVPに対してネガティブな評価がSNSなどで拡散されると、その後の事業展開に影響を与える可能性があります。
本質の理解が不十分な場合: 単にMVPを作って改善を繰り返すことだけがリーンスタートアップではありません。仮説検証と学習のサイクルを正しく理解し、実践することが重要です。
爆発的なイノベーションが生まれにくい可能性: 既存のニーズに対応していくプロセスが中心となるため、全く新しい市場を創造するような革新的なアイデアには繋がりにくいという指摘もあります。
リーンスタートアップの進め方(具体的なステップ)
1.アイデアと仮説の明確化:
誰のどのような課題を解決するのか? (顧客セグメントと課題)
どのような解決策(製品・サービス)を提供するのか? (ソリューション)
なぜそれがユニークで価値があるのか? (独自の価値提案)
どのようにして収益を上げるのか? (収益の流れ)
リーンキャンバスなどのフレームワークを活用して、ビジネスモデルの仮説を整理します。
2.MVP(実用最小限の製品)の構築:
仮説を検証するために最低限必要な機能に絞り込みます。
必ずしも動く製品である必要はなく、LP(ランディングページ)、デモ動画、手作業によるサービス提供などもMVPになり得ます。
3.計測と検証:
MVPをターゲット顧客に提供し、その反応を計測します。
A/Bテスト、インタビュー、アンケート、アクセス解析などを用いて、定量的・定性的なデータを収集します。
4.学習と分析:
収集したデータをもとに、仮説が正しかったのか、どこに問題があったのかを分析します。
顧客の行動やフィードバックから学びを得ます。
5.意思決定と次のアクション:
ピボット(方向転換): 当初の仮説が大きく否定された場合、事業の核となる要素(顧客セグメント、課題、ソリューションなど)を転換します。
反復(改善): 仮説の一部が正しく、改善の余地がある場合は、製品やサービスを改良し、再度「構築→計測→学習」のサイクルを回します。
撤退も選択肢の一つとして検討します。
リーンスタートアップの成功事例
Instagram(インスタグラム): 当初は「Burbn」という位置情報共有アプリでしたが、写真共有機能の人気が高いことに気づき、写真共有に特化したサービスへとピボットし、大成功を収めました。
Dropbox(ドロップボックス): オンラインストレージのニーズを検証するため、実際のサービス開発前に、Dropboxの利便性を説明するデモ動画を公開し、大きな反響を得てから開発を進めました。
食べログ: 当初は少数のユーザーからスタートし、ユーザーの意見を取り入れながら改善を繰り返し、日本最大級のグルメサイトへと成長しました。
ヤフー株式会社: ECサイトやアプリ開発など、様々な事業でリーンスタートアップの考え方を活用し、ユーザーのフィードバックに基づいた改善サイクルを回しています。
Techpit: プログラミング学習サービスを提供するにあたり、Twitterで顧客のニーズを調査し、多くの反響を得たことから事業をスタートさせ、迅速な成長を遂げました。
リーンスタートアップには重要な要素がある
リーンスタートアップで重要なことは、とにかくミニマムスタートを心掛けることです。
ビジネス要件はギリギリまで絞ることが大切です。
PDCAを高速で回す
企画→実行→振り返り→改善を2週間単位くらいで回転させると良いと思います。
高速PDCAを実施していると、A/Bテストなどを実施しなくても成長させられそうなポイントが見えてきます。
レバレッジを意識する
レバレッジとは、原義は「てこ(レバー、lever)の作用」。
レバレッジを意識して常にサービスを俯瞰すると、どこを優先してカイゼンを行えば効率的に成長させられるか感覚的に分かってくると思います。
アジャイル開発とリーンスタートアップの違い
・ アジャイルは製品開発手法
・ リーンスタートアップはビジネス開発手法
という点で違いがあります。
リーンスタートアップは時代遅れか?
一部では「時代遅れ」という意見も聞かれます。その理由として、SNSによる情報の拡散力や、よりスピーディーな開発モデルの登場などが挙げられます。しかし、リスクを抑えながら顧客ニーズを探り、事業の成功確率を高めるという本質的な価値は依然として有効であり、多くの企業や起業家にとって有用な手法であると言えます。重要なのは、手法そのものに固執するのではなく、その本質を理解し、自社の状況や目的に合わせて柔軟に活用することです。
リーンスタートアップは、不確実性の高い現代において、新しい価値を創造しようとする挑戦者たちにとって、強力な羅針盤となるでしょう。