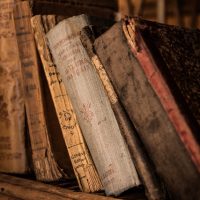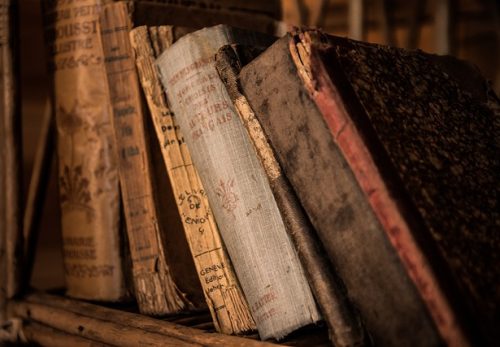特定保健用食品(トクホ)とは

特定保健用食品(トクホ)とは、からだの生理学的機能などに影響を与える関与成分を含み、健康増進法第26条第 1項の許可を受け、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品のこと。
平成30年9月3日現在、1,053件の食品が特定保健用食品の許可を受けています。
具体的には、以下のような特徴があります。
国の許可が必要: 食品ごとに有効性や安全性について国(消費者庁)が審査し、許可を与えます。許可されていない食品が「特定保健用食品」やそれに類似した名称を名乗ることはできません。
科学的根拠に基づいた効果: 「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収をおだやかにする」「コレステロールが高めの方に適する」など、特定の保健の目的が期待できる旨の表示が許可されています。これらの効果は、科学的なデータに基づいて審査されます。
許可マークの表示: 許可された食品には、人の形をデザインした「特定保健用食品」のマークが表示されています。これが、トクホであることを見分ける目印となります。
対象者: 主に、食生活の改善によって健康の維持増進を図りたいと考えている人が対象です。ただし、医薬品とは異なり、病気の治療や予防を直接の目的とするものではありません。あくまで、通常の食生活の範囲内で摂取し、健康の維持増進に役立てるものです。
特定保健用食品の種類
特定保健用食品には、いくつかの種類があります。
1.特定保健用食品(個別許可型): これが最も一般的なトクホで、企業が個別に申請し、国が審査・許可したものです。
2.特定保健用食品(規格基準型): 既に科学的根拠が十分に蓄積されている特定の関与成分について、国が規格基準を定めています。この基準に適合していれば、個別の審査を経ずに許可を受けることができます。食物繊維やオリゴ糖などがこれに該当します。
3.特定保健用食品(疾病リスク低減表示): 特定の栄養成分の摂取が、特定の疾病のリスクを低減させる可能性があるという表示が許可されたものです。例えば、「カルシウムは骨粗しょう症になるリスクを低減するかもしれません」といった表示がこれにあたります。
4.条件付き特定保健用食品: 特定保健用食品としての科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品について、「限定的な科学的根拠である」旨の表示をすることを条件として許可されるものです。
他の健康食品との違い
特定保健用食品(トクホ)とよく比較されるものに、「栄養機能食品」や「機能性表示食品」があります。
栄養機能食品: ビタミンやミネラルなど、特定の栄養成分の補給のために利用される食品です。国が定めた基準量を満たしていれば、届け出なしに企業の責任で機能を表示できます。
機能性表示食品: 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られますが、特定保健用食品のように国が個別に許可を与えるものではありません。
利用する上での注意点
特定保健用食品は、たくさん摂取すればより効果が高まるというものではありません。適切な摂取量を守ることが大切です。
バランスの取れた食生活が基本であり、特定保健用食品はあくまで補助的なものとして利用しましょう。
体質や体調によっては合わない場合もあるため、摂取して体に異常を感じた場合は、すぐに摂取を中止し、医師に相談してください。
特定保健用食品は、健康に関心を持つ消費者にとって、食品を選ぶ上での一つの目安となります。表示されている効果や関与成分、摂取目安量などをよく確認し、自身の食生活や健康状態に合わせて上手に活用することが大切です。