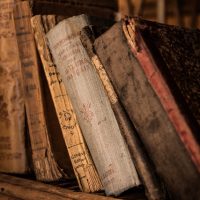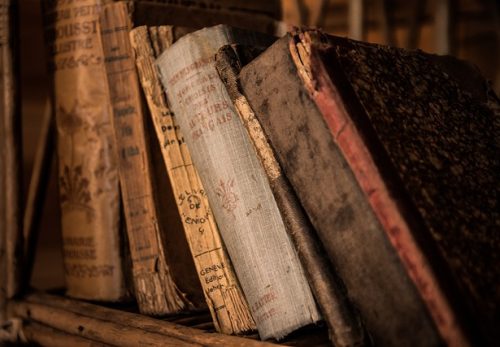Eコマース(Electronic Commerce)とは
Eコマース(Electronic Commerce)とは日本語で「電子商取引」で、インターネットなどのネットワークを介して契約や決済などを行う取引形態のことで、インターネットでものを売買することの総称です。
Eコマースの主な特徴
場所や時間に制約されない: インターネット環境があれば、24時間365日、どこからでも商品を購入したり、サービスを利用したりすることができます。
広範な顧客層へのアプローチ: 実店舗を持たなくても、国内外の広範な顧客にリーチすることが可能です。
データに基づいたマーケティング: 顧客の購買履歴や閲覧履歴などのデータを収集・分析し、個々の顧客に合わせたマーケティング施策を展開できます。
コスト削減の可能性: 実店舗の家賃や人件費などを抑えられる場合があります。
多様な商品・サービスの取り扱い: 物理的な制約が少ないため、多種多様な商品やサービスを取り扱うことができます。
Eコマース3つの分類
Eコマースは大きく3つに分類されます。
BtoB (Business to Business):企業対企業の取引
BtoC (Business to Consumer):企業対個人の取引
CtoC(Consumer to Consumer):個人対個人の取引
DtoC (Direct to Consumer): メーカーが仲介業者を通さずに、自社のECサイトなどで直接消費者に商品を販売する形態です。ブランドの世界観を伝えやすく、顧客との直接的な関係を築きやすいという特徴があります。
BtoE (Business to Employee): 企業が従業員向けに商品やサービスを割引価格で提供する形態です。福利厚生の一環として利用されることがあります。
GtoC (Government to Consumer): 政府や地方自治体が一般消費者に対して行う電子的なサービス提供です。
例: 税金の電子申告・納税(e-Tax)、住民票のオンライン申請
Eコマースのメリット
消費者側のメリット:
いつでもどこでも買い物ができる利便性
幅広い商品の中から比較検討できる
実店舗よりも安価に購入できる場合がある
口コミやレビューを参考にできる
事業者側のメリット:
商圏が全国・全世界に広がる
実店舗に比べて開業・運営コストを抑えられる場合がある
顧客データの収集・分析が容易
24時間販売機会がある
Eコマースのデメリット・課題
消費者側のデメリット:
商品を直接手に取って確認できない
配送に時間がかかる場合がある
個人情報漏洩のリスク
不良品や偽物が届くリスク
事業者側のデメリット:
競合が多く、価格競争に陥りやすい
集客のためのマーケティングスキルが必要
セキュリティ対策が不可欠
物流コストやシステムの維持管理コストがかかる
Eコマースの近年の動向と将来性
近年、スマートフォンの普及や決済手段の多様化、AIやAR/VRといった新技術の活用により、Eコマース市場はますます拡大しています。特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降は、非対面での購買行動が加速し、その重要性が一層高まりました。
今後は、以下のようなトレンドが注目されています。
オムニチャネル化: 実店舗とECサイトの垣根をなくし、顧客にあらゆる接点からシームレスな購買体験を提供する動き。
ライブコマース: ライブ動画配信を通じて商品を紹介し、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取りながら販売する手法。
ソーシャルコマース: SNS上で商品を発見し、そのまま購入できる仕組み。
サブスクリプションコマース: 定期的に商品やサービスを提供するビジネスモデル。
越境EC: 国境を越えて海外の消費者に商品を販売するEC。
Eコマース市場規模
BtoB
2018 年の BtoB-EC 市場規模は、344 兆 2,300 億円(前年比 8.1%増)となった。「その他」を除いた EC 化率は、前年から 0.8 ポイント増の 30.2%であった。
BtoC
2018 年の BtoC-EC 市場規模は、17 兆 9,845 億円(前年比 8.96%増)に。
EC 化率は、6.22%(対前年比 0.43 ポイント増)。
CtoC
2018 年 1 年間のフリマアプリの市場規模を推計したところ、6,392 億円となった。
Eコマースは、私たちの生活やビジネスに不可欠な存在となっており、今後も技術の進化とともにさらなる発展が期待されています。
参考:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課作成
平成 30 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備
(電子商取引に関する市場調査)報告書