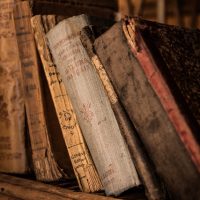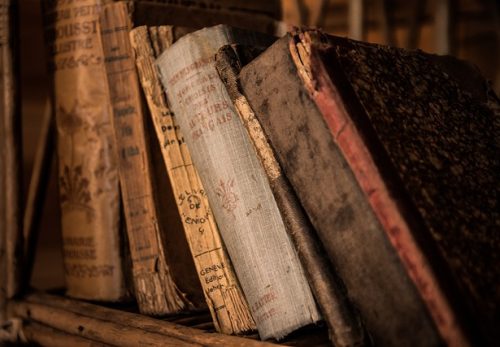カスタマージャーニーマップとは?
カスタマージャーニーマップ=顧客体験を可視化し、理解を深める羅針盤
カスタマージャーニーマップとは、ユーザーの行動をマッピングし、一覧にした見取り図のことです。
ユーザー行動が分かれば、例えばどこで離脱したか?振り返ることができるため、サービスの改善に大きく役立ちます。
カスタマージャーニーマップの歴史
そもそも、カスタマージャーニーマップは何を目的に作成され始めたのでしょうか?
一説によると、WEBマーケティングの分野でユーザー行動を把握するために生み出された手法と言われています。
最近は様々なシーンで使われるようになり、活用の場が広がりをみせています。
カスタマージャーニーマップを作成する目的とメリット
カスタマージャーニーマップを作成する主な目的と、それによって得られるメリットは以下の通りです。
顧客理解の深化
顧客が各段階で「何をし(行動)」「何を考え(思考)」「何を感じ(感情)」「どのような課題を抱えているのか」を具体的に把握できます。これにより、企業側の思い込みではなく、顧客の実態に基づいた理解が可能になります。
顧客視点での課題発見と改善機会の特定
マップを通じて顧客体験全体を俯瞰することで、顧客が不満を感じるポイント(ペインポイント)や、体験が途切れてしまう箇所、逆に満足度が高いポイントなどを発見できます。これらはサービス改善や新しい施策立案のヒントとなります。
施策の優先順位付けと最適化
顧客の課題やニーズが明確になることで、どの段階でどのような施策を打つべきか、その優先順位を判断しやすくなります。また、各タッチポイントでのコミュニケーションを最適化し、より効果的なアプローチが可能になります。
部門間の共通認識の醸成と連携強化
マーケティング、営業、開発、カスタマーサポートなど、顧客に関わる複数の部門が、顧客体験に対する共通の理解を持つことができます。これにより、部門間の連携がスムーズになり、一貫性のある顧客体験を提供しやすくなります。
コミュニケーション設計の精度向上
顧客が各段階でどのような情報を求めているのか、どのようなメッセージが響くのかを理解することで、より的確なコミュニケーション戦略を立てることができます。
データに基づくKPI設定と効果測定
各段階における顧客の行動や感情の変化を可視化することで、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、施策の効果を測定・評価しやすくなります。
リピーター施策への繋がり
購入後の顧客体験も含めてマップ化することで、継続利用やファン化を促すための施策検討にも役立ちます。
カスタマージャーニーマップの主な構成要素
カスタマージャーニーマップは、一般的に以下のような要素で構成されます。企業や目的によって項目はカスタマイズされます。
ペルソナ (Persona)
マップの主人公となる、具体的な顧客像。氏名、年齢、性別、職業、価値観、ライフスタイル、抱えている課題などを詳細に設定します。複数のペルソナがいる場合は、それぞれに対してマップを作成することもあります。
フェーズ/ステージ (Phases/Stages)
顧客が製品やサービスを認知してから購入・利用後に至るまでの、時系列的な段階。例えば、「認知」「興味・関心」「情報収集」「比較検討」「購入」「利用」「共有・推奨」など。
行動 (Actions/Doings)
各フェーズでペルソナが具体的にどのような行動をとるか(例:SNSで検索する、レビューサイトを見る、店舗に行く、問い合わせるなど)。
思考 (Thinking/Thoughts)
各行動をとる際に、ペルソナが何を考えているか、どのような疑問や期待を抱いているか(例:「この製品は本当に私の課題を解決できるのか?」「もっと安いものはないか?」など)。
感情/感情曲線 (Emotions/Feelings/Emotional Curve)
各フェーズや行動におけるペルソナの感情の起伏(嬉しい、不安、イライラ、満足など)を可視化したもの。折れ線グラフなどで表現されることが多いです。
タッチポイント (Touchpoints)
企業とペルソナが接するポイント。ウェブサイト、SNS、広告、店舗、カスタマーサポート、製品そのもの、口コミなど、オンライン・オフラインのあらゆる接点が含まれます。
課題/ペインポイント (Issues/Pain Points)
各フェーズでペルソナが直面する問題点、不満、障壁など。
機会/アイデア/施策 (Opportunities/Ideas/Measures)
明らかになった課題やペインポイントに対して、企業としてどのような解決策や改善策を講じることができるか、どのような施策が有効かといったアイデア。
KPI (Key Performance Indicators)
各フェーズにおける目標達成度を測るための具体的な指標。
カスタマージャーニーマップの作成ステップ
カスタマージャーニーマップは、以下のステップで作成するのが一般的です。
目的とゴールの設定
何のためにカスタマージャーニーマップを作成するのか、このマップを通じて何を達成したいのか(例:新規顧客獲得プロセスの改善、既存顧客のロイヤルティ向上など)を明確にします。
誰のジャーニーを可視化するのか、対象となる製品やサービスを明確にします。
ペルソナの設定
マップの主人公となる具体的な顧客像(ペルソナ)を設定します。顧客アンケート、インタビュー、アクセスデータ、営業担当者からのヒアリングなど、実際のデータに基づいて作成することが重要です。
フェーズ(ステージ)の設定
ペルソナがゴールに至るまでの主要な段階を時系列で設定します。業界や商材、設定したゴールによってフェーズの数や名称は異なります。
行動・タッチポイントの洗い出し
各フェーズでペルソナがどのような行動をとり、企業とどのような接点(タッチポイント)を持つかを洗い出します。ここでも実際の顧客データやインタビューが役立ちます。
思考・感情の記述
各行動やタッチポイントにおいて、ペルソナが何を考え、何を感じているのかを具体的に記述します。顧客の視点に立ち、共感することが重要です。
課題・ペインポイントの特定
ペルソナの行動、思考、感情の流れから、各フェーズで直面する課題や不満(ペインポイント)を特定します。
マッピング(可視化)
ここまで整理した情報を、横軸にフェーズ、縦軸に構成要素(行動、思考、感情、タッチポイント、課題など)を配置したマップ形式に落とし込みます。
改善策・施策の検討とKPIの設定
明らかになった課題やペインポイントに対して、具体的な改善策や新しい施策を検討します。
各施策の効果を測定するためのKPIを設定します。
共有と活用、そして見直し
完成したマップを関係者間で共有し、共通認識を醸成します。
マップを基に具体的なアクションプランを実行し、定期的に効果検証を行い、必要に応じてマップ自体も見直します。市場環境や顧客の行動は変化するため、マップも一度作ったら終わりではなく、継続的にアップデートしていくことが重要です。
カスタマージャーニーマップ作成時の注意点と成功のポイント
「企業目線」ではなく「顧客視点」で作成する
企業の「こうあってほしい」という願望ではなく、実際の顧客データや調査に基づいて、顧客のリアルな体験を描き出すことが最も重要です。
思い込みや憶測を排除する
データや事実に基づいて客観的に作成することを心がけます。可能であれば、実際の顧客にインタビューを行うのが理想的です。
ペルソナを具体的に設定する
曖昧なターゲット像ではなく、具体的な一人の人物としてペルソナを設定することで、より共感しやすく、リアルなジャーニーを描きやすくなります。ただし、細かすぎる設定が必ずしも良いとは限らず、目的に応じた粒度で設定します。
関係者を巻き込んで作成する
マーケティング部門だけでなく、営業、開発、カスタマーサポートなど、顧客に接する様々な部門のメンバーが参加して作成することで、多角的な視点が取り入れられ、より実態に即した、かつ全部門で共有しやすいマップになります。
シンプルで見やすいマップを心がける
情報が多すぎると複雑で分かりにくくなるため、目的やターゲットに合わせて情報を整理し、視覚的に分かりやすいマップを作成します。
完璧を目指しすぎない
最初から完璧なマップを作ることは難しいです。まずは叩き台を作成し、関係者からのフィードバックや実際のデータに基づいて、継続的に改善していくことが大切です。
作成して終わりではなく、活用することが目的
マップはあくまでツールです。マップから得られた気づきを基に、具体的な施策に落とし込み、実行し、改善していくことが重要です。
定期的な見直しと更新
顧客の行動や市場環境は常に変化します。一度作成したマップも、定期的に見直し、最新の状況に合わせて更新していく必要があります。
カスタマージャーニーマップのテンプレートと活用事例
インターネット上には、カスタマージャーニーマップの無料テンプレートが多数公開されています(例:Miro, HubSpot, Canva など)。これらを参考に、自社の目的に合わせてカスタマイズすると良いでしょう。
活用事例としては、以下のようなものがあります。
BtoCビジネス
オンラインショップでの購買プロセス、旅行予約体験、店舗でのサービス体験など。
BtoBビジネス
ソフトウェア導入検討プロセス、法人向けサービス契約プロセスなど。
製品・サービス開発
新規製品・サービスの顧客体験設計、既存製品・サービスの改善点発見など。
UX(ユーザーエクスペリエンス)デザイン
ウェブサイトやアプリのユーザーインターフェース改善、顧客満足度向上など。
例えば、あるアパレルブランドが「オンラインで服を購入する顧客」のカスタマージャーニーマップを作成する場合、「SNSで商品発見」→「ブランドサイトで詳細確認」→「レビューサイトで口コミチェック」→「カート追加」→「購入手続き」→「商品到着」→「試着」→「SNSで感想投稿」といったフェーズを設定し、各フェーズでの顧客の行動、思考(「この服かわいい!」「サイズ合うかな?」「他の人の評価はどうだろう?」)、感情(ワクワク、不安、満足)、タッチポイント(Instagram、ブランド公式サイト、レビューブログ、配送業者)、課題(「サイズ感が分かりにくい」「送料が高い」)などを洗い出し、そこからウェブサイトの改善点やSNSでのコミュニケーション施策などを検討することができます。
カスタマージャーニーマップは、顧客中心の考え方を組織に浸透させ、より良い顧客体験を創造するための強力なツールです。
ペルソナを設定する
カスタマージャーニーマップを作成するためには、まず、ペルソナを設定する必要があります。
なぜなら、ペルソナを設定する理由として、年齢、男女の別によって行動が変化する場合があり、さらにITリテラシーが高い、低いによってもアクションが変わる場合もあるためです。
仮説主導でカスタマージャーニーマップを作成する
仮説で構いませんので、カスタマージャーニーマップのラフスケッチを作成しましょう。
カスタマージャーニーマップのラフができたら、チームでレビューをしながらブラッシュアップすることが望ましいです。
チームレビューでは、ポジションによって見方、考え方が全然異なるので色々な意見が出ることにきっと驚くことと思います。
AISASフレームワークとGAを使って考えてみる
まずは私の場合、カスタマージャーニーマップのラフは、AISASフレームワークをベースに作成しています。
AISASとは、購買行動プロセスの頭文字をとったもので、購買まで以下の5つのプロセスを辿ると言われています。
・ Attention(注意)
・ Interest(関心)
・ Search(検索)
・ Action(購買)
・ Share(情報共有)
次に、GAを見ると離脱ページが分かるので、どのポイント・どのページで離脱しているかをカスタマージャーニーマップに情報を反映していきます。
いかに購入に繋げるか?を考える
WEBプロモーションにおいては、お客を呼び込むだけでなく、ページから離脱させず、いかに購入までつなげるかが重要な鍵になります。
そのため、キャッチーな言葉で気を引くだけでなく、画面遷移数の増減、フォームの入力数増減などサイト全体を総合的に考察する必要があります。
効果測定・改善プロセスでは、A/Bテストによって変更前、変更後の数値を確認をしながら進めていきましょう。
どのようにプロモーションすれば効果的か?を考える
WEBプロモーションを行う上で、どのようにプロモーションすれば効果的か?を考えて、ステップごとにプロモーション方法を書き出してみましょう。
付箋などを貼り付けながらブレストすると効果的かと思います。
ブレストペルソナで設定したユーザーになりきってアイデアを出すのがポイントです。
カスタマージャーニーマップ作成ツールは何がいいか?
カスタマージャーニーマップ作成ツールはエクセルか、パワーポイントで十分かと思います(私の場合)。
色々な便利ツールがありますが、WEBプロモーションの現場では、あくまで「購入に繋げる」ことが目的で、カスタマージャーニーマップを作ることが目的ではないためです。
まとめ
・ 顧客視点でカスタマージャーニーマップを作成する
・ ペルソナで設定したユーザーになりきってアイデアを出す
・ カスタマージャーニーマップを作るためのツールは自分の使いやすいツールを使うとよい